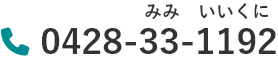【東京都】補聴器購入で補助金を受け取るには?申請方法や条件を解説
ファミリー補聴器店長の吉野です。本記事では、補聴器に関する補助金の申請方法を解説します。
東京都では、条件に該当していれば福祉課に申請して補聴器の購入費用の補助を受けられます。補聴器の購入を検討している方や、ご家族に補聴器が必要な方がいる場合はぜひご参考にしてください。
Contents
【東京都】補聴器購入で補助金を受け取れる?
補聴器にかかる経済的負担を軽減するため、障害者総合支援法では「補装具費支給制度」が定められています。
「補装具費支給制度」は身体障害者福祉法に定められた「障害程度」に該当する方を対象とするため、受けるには医師の診断や福祉課への申請が必要です。
障害者手帳の交付対象でない場合や、一定の所得がある場合は障害者総合支援法による補助金は受けられません。
その際は自治体独自の助成金制度が受けられないか、お住まいの地区の福祉課へ相談しましょう。東京都青梅市では「高齢者補聴器購入費助成事業」により上限40,000円の助成が受けられます。
補助制度の内容について解説
「補装具費支給制度」について詳細を解説します。具体的には、以下の3点についてです。
- 費用について
- 支給品の個数
- 修理について
補助制度について知り、補聴器の使用を検討しましょう。
①費用について
補聴器は「主材料」「工作法」「基本構造」「付属品」などにより基準額が定められています。例えば、高度難聴用ポケット型だと44,000円、高度難聴用耳かけ型は46,400円などです。
原則、基準額の1割を自己負担として、費用が支給されます。
補装具費用の算定は、購入したときや修理したときのいずれかにおいて、「告示により算出した額」又は「現に補装具の購入又は修理に要した費用の額」の低い額を基準額として定められます。
②支給品の個数
補聴器の場合は、左右どちらか1個が支給対象です。ただし支給対象者になる方の状況や年齢、職業などを考慮して2個支給が受けられる場合があります。
一般的に補聴器は両耳に装着して使用するため、自治体に申請する際に相談しましょう。
③修理について
補聴器の購入だけでなく、修理についても助成金を受けられます。基本的な修理部位と価格は基準表によって定められており、そのほかだと原価計算や市場価格に基づいて支給額が決まります。
もし、補聴器の修理を検討している場合には、修理費用を支給してもらえる可能性があるのでぜひご検討ください。
補助金の申請方法を紹介
補聴器の補助金制度を受けるためには、以下のような手順で申請をします。
- 申請:福祉課などへ身体障害者手帳を提出し、補聴器の補助金や支給等の相談をする。
- 医師の診断:補聴器相談医に相談し、補聴器購入費用給付診断書・意見書を記入してもらう。
- 補聴器の見積り:補聴器販売店で、医師の意見書をもとに補聴器の見積書を記載してもらう。
- 書類の提出:福祉課に用意した書類を提出する。
- 支給の決定:補聴器支給の判定が行われる。
- 支給決定通知が自宅に届く:支給決定通知を補聴器販売店に提出すると補聴器を受け取れる。
支給の判定には、以下のような方法・流れがあります。
- 来所判定:申請者本人が申請しに行く。
- 書類判定:意見書により、センターが判定する。(高度難聴用(両耳)/重度難聴用/耳あな型/骨導式)
- 区市町村判断:指定医の意見書により判断する。(高度難聴用(片耳)/人工内耳用音声信号処理装置の修理)
これらの手順を踏むことで、補聴器の補助金を受けられます。
補助金を受ける条件を紹介
「補装具費支給制度」を受けることができるのは、補装具を必要とする障害者や障害児、難病患者などで、障害者手帳の取得が必要です。
そのほか、所得によって受けられない場合もあります。障害者やその配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、補装具費の支給対象外です。
「補装具費支給制度」が受けられない方は、自治体独自の助成制度を利用できないか確認しましょう。東京都では次のような条件で、難聴児と高齢者に向けて助成が行われています。
【軽度・中等度難聴児の場合】
- 両耳で30デシベル以上の難聴
- 障害者手帳の交付対象者ではない
- 18歳以下の児童
- 補聴器によって言語習得効果が期待できると医師の判断に基づく
【高齢者(65歳~70歳以上)の場合】
- 医師の診断により補聴器が必要であること
- 障害者手帳の交付対象者ではない
- 世帯所得の助成制限に当てはまらない(住民税非課税の方のみ、規定所得上限内の場合もある)
- 過去に補聴器の助成金を利用していない(一定期間経っている)
お住まいの自治体の福祉課・高齢者支援課までお問い合わせください。
まとめ:東京都で補聴器を購入する際には、補助金を申請しよう!
補聴器は高額な商品のため、簡単には購入を決められないかと思います。経済的負担が大きな壁になっている場合は、「補装具費支給制度」や地方自治体の補助金制度の利用をご検討ください。利用するためには条件があるため、お住まいの自治体の福祉課で相談しましょう。
【Q&A】
Q1:補助金の申請方法は地方自治体で違う?
A1:申請方法は基本的に同じです。自治体独自の補聴器の購入助成金(補助金)制度は、受けられる条件や内容が自治体によって異なります。
Q2:補聴器を購入するときの補助金は誰でも申請できる?
A2:定められている条件に当てはまらない方は申請できません。お住まいの自治体の福祉課にご相談ください。